皆さんの会社でもITエンジニアの採用に苦戦していませんか?実は、日本全体でIT人材の不足が年々深刻になっています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の波やAI技術の進化に伴い、どの企業も優秀なエンジニアを求めています。
しかし「求人を出しても応募が来ない…」という声も多く、残念ながら「待っていても人は来ない」という状況が今の日本です。そこで注目されているのが外国人IT人材の採用。本記事では、国内IT人材不足の現状と、外国人ITエンジニア活用の最新動向について、データや事例を交えて解説します。

日本のIT人材不足の現状
日本ではここ数年、ITエンジニア不足が顕著です。経済産業省の調査によれば、2018年時点で約22万人ものIT人材が不足しており、需給バランスのギャップは拡大の一途をたどっています。特にAIやクラウドなど先端分野需要増で人材獲得競争は激化しています。いくつか数字で現状を見てみましょう。
将来予測
2030年には、需要と供給の差が最大約79万人(2021年の経産省の報告書)に達する恐れがあると試算されています。まさに前代未聞のIT人材不足です。
企業の実感
採用サービスの調査では、約7割の企業が「デジタル人材が不足している」(2024年の帝国データバンク調査)と回答しています。特にエンジニア職の欠員を感じる企業が多い状況です。
求人倍率
ITエンジニア職の有効求人倍率は3.6~3.7倍と非常に高水準で、全職種平均(約1.5倍)の倍以上です。この数字は、求職者1人に対し求人が3~4件あるという計算で、いかにITエンジニア職が「売り手市場」であるかが分かります。
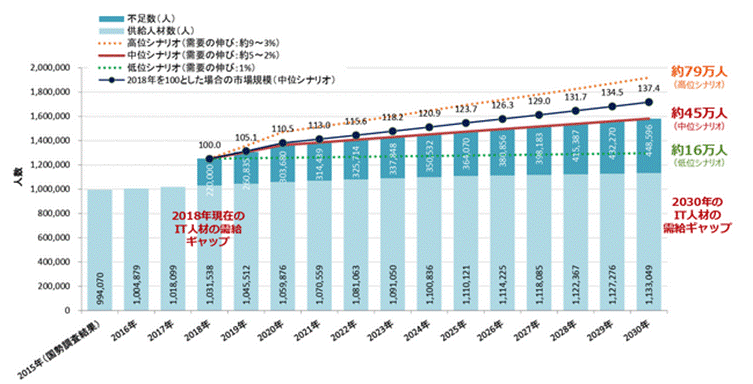
出典:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf
これらのデータからも、「欲しい人材は他社も奪い合っている」といった厳しい状態が読み取れ、IT人材を国内だけで集める事は大変厳しい現実です。特に、中小企業やスタートアップの状況は深刻で、大企業に人材を奪われてしまう傾向があるため、「募集をかけても1年間応募がゼロ…」「新卒は全く取れない」という話も珍しくはありません。このままでは事業戦略の実行、各種プロジェクトの遅延、新規事業の停滞など、企業側の成長にブレーキがかかってしまいます。そこで解決策の一つとして期待されているのが外国人のIT人材の活用なのです。
外国人IT人材活用の最新動向
日本のIT業界では、人手不足を補うために、外国人のIT・CAD等のITエンジニアの採用が年々増加傾向にあります。このグラフが示すように、2024年時点のIT業界で働く外国人は約9.1万人に達し、この10年で約3倍に増えています。
出典:IT業界で働く海外人材、10年で約3倍となるも伸び率は鈍化、ネパール、インドネシア、ミャンマーなどが大幅増、出身国は多様に | ヒューマンホールディングス株式会社のプレスリリース
これは、日本で働く外国人労働者数が過去最高を更新し続けているという流れの中で、IT分野でもその傾向が顕著に現れています。特に高度な専門知識とスキルを持つ人材が活躍しているケースが多いです。具体的に見ていくと、IT分野では、外国人労働者の約75%が「技術・人文知識・国際業務」、一般的には「ギジンコク」と呼ばれる専門的分野の在留資格で就労しています。

外国人エンジニア採用を積極化する企業も増えており、日本の技術革新を支える戦力となっています。大胆なグローバル採用戦略で有名な企業として、例えばメルカリ社では、2018年の新卒エンジニア採用で50人中44人を外国籍人材が占め、その後も採用を拡大し2021年には社員の約半数が海外出身であると報じられています。
また、ある大手IT企業ではインド出身のAIエンジニアを積極的に採用し、新規プロジェクトの中核メンバーとして活躍してもらうことに成功しました。この企業では採用プロセスも英語対応に変え、入社後も社内公用語を一部英語化するなど柔軟な対応を行っています。
その結果、そのインドから就労している人材は、プロジェクトを大成功に導いただけでなくチーム全体の刺激にもなったそうです。さらに楽天のように英語を社内公用語にして海外から優秀な人材を呼び込み、多国籍から集めた人材で開発組織を構築しているケースもあります。
楽天では2012年の英語公用語化以降、社員の国籍が100カ国以上に広がったとされています。こうした事例からも分かるように、外国人IT人材の登用はもはや一部の企業だけの話ではなく、国内全体へと広がる一つのトレンドとなっています。近年ではインドやベトナムのみならず、ネパールのような新興国から優秀なエンジニアを受け入れるケースも増えています。
外国人IT人材採用の基本ステップ
外国人エンジニアの採用を成功させるには、いくつかの基本的なステップと事前準備が欠かせません。ここでは採用プロセスの流れに沿ってポイントを整理します。
採用計画の立案と社内の合意形成
まず、なぜ外国人を採用するのかという目的を明確にします。業務内容に応じた必要なスキルやポジション、言語サポートや教育等の受け入れ体制を社内で話し合いましょう。
例えば「日本人だけでは〇〇の開発が進まないので海外から○名採用したい」「海外から採用した人材は将来的に〇〇といった役割を担ってほしい」「その人材にも活躍してもらい、これまでの風土を変えていきたい」といった短期・中長期のビジョンを共有し、上層部や現場の意向も確認のうえ、合意を取ります。
国別のビザ要件や来日する際の語学力など、募集前の情報収集も重要なので把握しておきましょう。
求人チャネルと募集方法の工夫
次に採用チャンネルには何があるのかについて、情報収集しましょう。自社サイトや国内向けの求人媒体だけでなく、外国人エンジニアにリーチできる手段を模索し、積極的に活用しましょう。
・外国人IT人材に強い人材紹介会社に依頼する
・英文の求人票を自社サイトやLinkedIn等に掲載する
・海外の技術イベントやSNSで自社をアピールする
・自社の英語版ホームページや技術ブログを充実させ、グローバル人材に響く情報発信をする
・社員の知人やネットワークを活用して人材を探す
募集要項を出す際の注意点
「必要な日本語レベル」や「待遇」を明確にしつつ、企業側の特徴や魅力も伝えることが大切です。会社のグローバルな魅力や先端プロジェクト内容などを盛り込みましょう。
加えて、入社後どのような仕事に携わってもらうのか、どのような成長機会が提供できるのかといった点も重要です。さらに、初回面談では、誤字・脱字・敬語の使い方を含めた日本語レベルについて、過度にこだわりすぎないこともポイントです。外国人採用の際、日本語力だけで候補者の職務能力を判断しないよう注意が必要です。
選考プロセスと評価ポイント
外国人の候補者には、柔軟な選考フローを設計しましょう。日本在住の外国人だけではなく、海外に在住している外国人を対象にする場合、オンライン面接やコーディングテストを活用し、遠方からでも参加しやすくします。
評価の際は技術スキルだけでなく、その人材のパーソナリティー、コミュニケーションを取ろうとする意欲、さらには異文化にも適応できそうかといった可能性も見ることが重要です。例えば技術面接に加えて、雑談も含めたカルチャーフィット面接を組み合わせ、多面的に人柄と能力を知ることで、ミスマッチを防ぐことができます。
英語でのオンライン面談もぜひ検討しましょう。外国人に特化した人材紹介会社であれば、無料で通訳してくれることもあります。社内に英語話者がいなければそういったサービスも活用し、言語の壁で本来の実力が見えないことを未然に防ぎます。現場のエンジニアにも協力してもらい、専門知識の見極めとチームへの適応力を総合評価できるとベストです。

内定後のビザ手続き・受け入れ準備
採用が決まったら、ビザ(在留資格)手続きや受け入れ準備に速やかに取りかかります。海外在住者を呼ぶ場合は在留資格認定証明書の申請、国内在住であれば在留資格の変更などが必要です。これら法的手続きは複雑なので、行政書士など専門家のサポートを受けると安心です。
同時に、来日する人には住居探しや赴任スケジュールの調整、入社書類の多言語化など細やかな準備を行いましょう。人事担当者にとってビザ取得や各種書類準備は負担になりがちですが、ここをしっかり対応することで後々のトラブルを防げます。外国人に特化した人材紹介企業や支援サービスを提供している企業を活用すると、サポートを受けることができるケースもあります。
オンボーディングと定着支援
入社後は、外国人エンジニアがスムーズに職場に馴染む支援が欠かせません。例えば、メンター制度を導入して日本人社員が業務や生活面をサポートしたり、社内ルールや日本のビジネスマナーを教えるオリエンテーションを実施すると良いでしょう。チームにはお互いの文化の違いを理解し尊重する姿勢を促します。社内公用語を英語併用にする取り組みも効果的です。
また、業務外でも交流できる機会(食事会やイベント)を設け、「仲間」の一員として迎え入れる雰囲気づくりを心がけます。日常生活の悩み相談窓口を設置する企業もあります。こうしたフォローによって「せっかく採用したのにすぐ辞めてしまった…」を防ぎ、長期活躍してもらえる可能性が高まります。
以上のステップを踏むことで、初めて外国人を採用する場合でも準備を進めることができます。専門家の力を借りながら進めれば、大きな問題なく進行できるでしょう。
外国人採用のためのポイント
外国人IT人材の採用には、多くのメリットがある一方で、事前に理解しておくべき課題も存在します。良い面と注意すべき面を整理してみましょう。
高度なスキル人材の確保
海外には優秀でチャレンジ精神や成長意欲の高いIT人材の巨大なプールがあります。例えば、ネパールの一流大学で学んだエンジニアや最新技術に精通した人材が採用できれば、英語も話せることから自社の技術力・開発力を大きく強化できます。
特に、圧倒的にITや機械設計を含むCAD人材が不足している建築業界や製造業では、外国人エンジニア採用が課題解決の最短のルートになる場合もあります。実際、日本で就労ビザを取得できる外国人は一定の学歴やキャリアを持つため、質の高い人材が集まりやすいという面もあります。
社内の活性化・イノベーション促進
異なる価値観やバックグラウンドを持つメンバーが加わることで、組織やチームに新しい視点やアイデアがもたらされます。長年同じ企業で働いている社員や日本で育ち似たような価値観を持つ人だけでは思いつかない発想で、活発な議論が生まれ組織が活性化します。
実際、海外での経験があるエンジニアは尖った視点や新鮮な知見を持ち込んでくれることが多く、イノベーションの推進力にもなります。さらに、多国籍な職場は社員にとって刺激となり、学ぶ姿勢やハングリー精神が醸成されるという風土を変えるといった効果も期待できます。
組織のグローバル化と競争力向上
日本人同士で仕事をしていると、多言語を使う機会が少ないです。国際的な教育期間である「EF Education First」(スウェーデン本社)が毎年発表している、世界の非英語圏の国々の英語能力を評価する指標EF EPI(EF Ensligh Proficiency Index)において、例えばIT人材を日本に送り出している国の第4位(厚労省が発表した2024年10月時点での技術・人文知識・国際業務資格保有者数)であるネパール人の英語スコアは512で115ヵ国中56位(アジア6位)、日本人のスコアは454で115ヵ国中92位(アジア16位)と大きく差が出ており、日本は世界平均477を下回っています。語学面だけを見ても、英語を使う環境や多文化共生の職場は、日本人社員にとっても魅力ある環境となるでしょう。
また、働き方といった側面においては、外国人が働きやすい職場を整備する中で、無駄な長時間労働の見直しや柔軟な働き方の導入も進み、日本人社員にとってもメリットが大きいです。さらに、社内に多様な人材がいることで、自社製品・サービスのグローバル展開にも弾みがつきます。外国人社員が北米進出のキーマンになった、という事例もあります。現地の市場知識や語学力を活かして活躍してくれる可能性という観点からも、外国人採用は企業の国際競争力を高める投資とも言えるでしょう。

言語・コミュニケーションの壁
最も大きな課題はやはり言葉の問題です。日本語が母語でない社員との意思疎通には、想像以上の工夫が必要です。専門的な会話やちょっとしたニュアンスの違いで誤解が生じ、生産性に影響することもあります。例えば会議中、「〇〇してください」という指示に対して、「はい」と回答した場合、国によって「理解して了解した」という意図と「理解はしていないけど言われたことを聞いた」、或いは「理解しているつもりが実は…少し分からないところがある」ということも。
<対策>
メールで改めて指示を送る、翻訳ツール等を使って英語でも伝える等、念入りなコミュニケーションを取る。「わからない時は何度でも聞いてOK」といった遠慮せず確認し合える関係性や雰囲気づくりをおこなう。
文化・価値観の違い
言葉以上に見落としがちなのが文化の差です。仕事に対する姿勢や報連相の頻度、上下関係の感じ方など、国が違えば常識も違います。日本特有の年功序列やハンコ文化、会議での暗黙の了解、根回しなどは、外国人には奇異に映るかもしれません。「郷に入っては郷に従え」と放置すると誤解から双方にフラストレーションが溜まります。
<対策>
入社までの期間、日本の職場文化を丁寧に説明し、入社後はメンターを付けて質問しやすくする日本企業側の意識改革と努力も必要。多様な価値観を受け入れる事前のトレーニングや入社する人材の出身国の勉強会など、異文化コミュニケーション研修等を行う。これによって、お互い歩み寄る姿勢を持つ。
ビザなど法務手続き・労務管理の複雑さ
外国人を雇用するには避けて通れないのが在留資格(ビザ)関連の手続きです。ビザの申請・更新や各種行政への届け出など、専門知識が要求される業務が多々あります。さらに契約書の作成や社会保険の適用確認など、日本人採用では意識しないポイントにも気を配る必要があります。例えば、外国人社員には母国の兵役義務がある場合があり、長期就業に制約が出る可能性も考慮しなければなりません
<対策>
社内だけで抱え込まず専門家に相談する。例えば、行政書士や社労士の力を借りて適切に対応すれば、リスクを最小化できる。
また、入社後もビザ期限の管理や更新サポートを行い、安心して働けるようにすることも企業の責任。
採用コスト・定着コストの増加
外国人採用は、日本人の採用に比べてコストや手間がかかる傾向があります。ビザ取得費用や語学支援、渡航費、引越補助など追加の負担は避けられません。せっかく採用しても文化のミスマッチで早期離職されてしまうと大きな損失となってしまいます。
<対策>
予め、効率的な採用プロセスとオンボーディング計画を組む。外国人採用に特化した専門家の支援や適切な媒体を活用した必要人材の採用と入社後の計画的な研修やフォローで早期戦力化と定着が図れる。
来日前、就業開始から数か月間の最初に手厚く支援することで、長く活躍してもらい、投資が回収できるイメージを持つ。長期的に見れば、外国人エンジニアがもたらす価値は投資以上のものになるはず。
まとめ:今すぐ動くべき理由
深刻化するIT人材不足の中、「待っていても人は来ない」のは明らかです。日本企業がこれまで通り新卒一括採用や国内中途だけに頼っていては、必要なエンジニアを確保できない時代に突入しています。だからこそ今こそ動くべきなのです。
まずは一歩踏み出すことが大切。幸い、政府も高度外国人材の受け入れを促進しており、高度人材ポイント制や在留資格の緩和措置など企業を支援する制度も整いつつあります。先述のように既に多くの企業が外国人採用に乗り出し成果を上げています。「うちはまだ早いかな」「日本語ができないと厳しいのでは」と尻込みしている間にも、優秀な人材は他社や海外へ流れてしまいます。
企業としては、まず社内で問題意識を共有し危機感を持つことがスタートです。そして、小さくても具体的な行動を起こしましょう。例えば、外国人採用に関連する情報収集したり、社内受け入れ体制を検討したり、できることから着手してみてください。幸い、本記事で述べたようなメリットが得られれば、きっと社内からも「やって良かった」という声が出てくるはずです。
IT人材不足は待ったなしの状況ですが、視野を広げて海外に目を向ければ道は開けます。多様な人材を受け入れてこそ生まれるイノベーションもあります。ぜひ「今動く」ことで未来の競争力を手にしましょう。優秀なIT人材との出会いは、すぐ目の前かもしれません。日本の企業がこの難局を乗り越え、さらなる成長を遂げるために、皆さんの前向きな挑戦を応援します。






